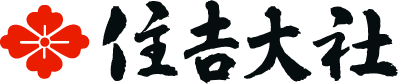私どもが一身を捧げて奉仕する住吉大神は、神話の中で伊弉諾尊が禊祓をおこなわれた際、海の底・中・表から出現せられた三神を合わせてお祀り申し上げています。海の底は、龍宮城に例えられるように、真珠や珊瑚などの宝物や海底資源があります。海の中ほどは漁獲などの海の幸が得られます。海の表では、船路によって人々の往来があり様々な文化や舶来品がもたらされました。心身を浄化し、幸を恵まれる、そのありがたいご神徳を輝かせられるご存在が、我々が奉斎いたします住吉大神であります。
当社には、大切に守られてきた文化財が数多くあります。神社建築では最古の様式を伝える本殿四棟が国宝に指定されるほか、重要文化財、国の登録文化財に指定された多数の建造物や宝物を有しています。境内には国と市の史跡を含み、大都会である大阪では貴重な鎮守の森、名勝の反橋(太鼓橋)があり、これらは大阪府みどり百選にも選定されていますが、松のある森厳な社叢は今も昔も変わりません。
また、1800年を超える悠久の歴史を振り返ってみますと、神功皇后による御鎮座、住吉津の開港、朝廷の祭祀、遣唐使の発遣、歌人の尊崇、文学作品の舞台、北前船や菱垣廻船の航海守護など、皇室を始め庶民の住吉信仰に至るまで特筆すべき事柄が数多くあります。
そして、年間におこなわれる大小の祭典は約140件もある中で、祈年祭・新嘗祭の大祭をはじめ、踏歌神事、白馬神事、御結鎮神事、松苗神事、卯之葉神事、御田植神事、住吉祭、宝之市神事などじつに多彩な神事がありますが、ご崇敬の皆様がご参列や拝観を楽しみにされるものも少なくありません。
これら有形無形の伝統文化は住吉大社の信仰の根源であります。これらを厳修、継承することは住吉大社発展の力であると確信しています。私どもは、住吉信仰を次世代に伝承するための責務を果たすよう、神明奉仕に努めてまいる所存です。
どうかご崇敬の皆様方には格別のご支援ご協力を賜わりますよう、謹んでお願い申し上げます。

住吉大社 宮司
神武 磐彦
(こうたけいわひこ)